2006年8月にあったIAU(国際天文学連合)の総会において、冥王星が惑星から外されることになりました。その背景には、 最近の観測や研究で太陽系や惑星について、たくさん新しい発見がありました。この機会に、惑星を含め太陽系全体を眺め直してみることにします。
内 容
天体を肉眼で観測していた頃、天体には2種類あることが知られていました。星座を形作る星と、 星座の間をいったりきたりする星です。前者を恒星と呼び、後者には太陽・月そして惑星がありました。
その頃の惑星は、水星・金星・火星・木星・土星の5つです。その後、惑星は太陽の周りを回る天体であることがわかりました。 地球も太陽の周りを公転していることで、惑星の仲間に加わりました。次に、 望遠鏡が発明され、また写真を使って天体を観測するようになって、いくつかの天体が惑星に加えられました。 この時に惑星の仲間入りをしたのが、天王星・セレス・海王星でした。ところがセレスは他の惑星と違うところがいっぱいありました。 非常に小さく暗いということ、ほぼ同じ公転半径を持つ天体が続々と見つかってきたことです。 そこで、セレスはパラス・ジュノー・ベスタやその他のよく似た天体とともに小惑星とされたのです。
その後も、太陽系の惑星探しが続けられました。そして1930年に発見されたのが冥王星です。 この時点で、太陽系の惑星は水星・金星・地球・火星・木星・土星・天王星・海王星・冥王星の9つになりました。
ふつう恒星はまたたくのに惑星は、またたかないので見分ける事ができるといわれています。この方法は土星までは使えますが、 天王星や海王星は見えないので無理です。恒星がまたたいて見えるのは、その形が点状で、大気の揺らぎで、 位置がずれたり、光が強められたりするからです。逆に惑星は、大きさに広がりを持っているため、 大気の揺らぎの効果を受けずまたたきません。天王星や海王星も、少し大きな望遠鏡で見ると円盤状に見えます。
このような点以外にも、冥王星は惑星としては変わっているといわれ続けてきました。 次に、冥王星がどのように変わっているかを検証します。
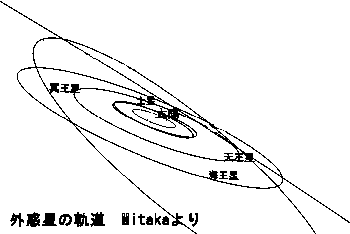 冥王星が他の惑星と大きく異なると発見時から指摘されていたことの一つめは、軌道の離心率が大きいことです。
この数値が大きいほど、軌道の形は細長い楕円形になります。また、太陽に近づいたときと離れたときの太陽までの距離の差が大きくなります。
冥王星のこの値は0.25で、これに次ぐのが水星の0.21です。
その他の惑星が0.1より小さいことを考えると、この値はかなり大きいといえます。
離心率が大きいことで、冥王星は海王星より太陽に近づくことがあります。そのときは、
水金地火木土天海冥(関西では「すいきんちかもくどってんかいめい」と読みます)ではなく水金地火木土天冥海とかいっていました。
冥王星が他の惑星と大きく異なると発見時から指摘されていたことの一つめは、軌道の離心率が大きいことです。
この数値が大きいほど、軌道の形は細長い楕円形になります。また、太陽に近づいたときと離れたときの太陽までの距離の差が大きくなります。
冥王星のこの値は0.25で、これに次ぐのが水星の0.21です。
その他の惑星が0.1より小さいことを考えると、この値はかなり大きいといえます。
離心率が大きいことで、冥王星は海王星より太陽に近づくことがあります。そのときは、
水金地火木土天海冥(関西では「すいきんちかもくどってんかいめい」と読みます)ではなく水金地火木土天冥海とかいっていました。2番目は、軌道傾斜角が17°と大きいことです。次に大きい水星が7°ですからかなり大きいといえます。 この値が小さいと、惑星は星座間の太陽の通り道である黄道(こうどう)の近くを通ることになります。 冥王星が地球・太陽から遠く離れていることと合わせて考えると、黄道から17°も離れることがあることを示しています。
3番目は、大きさが小さいことです。その半径は約1200kmです。 これは、水星(半径2400km)のほぼ半分の大きさで、質量では30分の1です。 さらに、月(半径約1700km)や木星の衛星ガニメデ・イオなどより小さいことがわかっています。
4番目に、どのグループに属するかという問題があげられます。惑星をその特徴で分けたとき、 冥王星だけどのグループにも属さないことになります。このことについては後で詳しく説明します。
そのほかにも、衛星カロンとの関係も不思議です。衛星カロンは直径が冥王星の半分もあります。 質量で1/4です。次に大きな衛星を持つ地球では、衛星月の半径は約1/4、質量は約1/80です。 冥王星は非常に大きな衛星を持っていることがわかります。このため、冥王星はカロンの公転に振り回されています。
その後、冥王星とよく似た天体が多数見つかり始めました。
太陽系の外側がどのようになっているかを最初に考えたのがオールトです。オールトは、公転周期が200年以上の長周期彗星に注目しました。 長周期彗星の中には、木星などの大きな惑星の引力の影響を受けていない物があり、これらは地球の公転半径の5〜15万倍 (5〜15万天文単位)離れたところからやってくることをつきとめました。そこで、太陽から5〜15万天文単位離れたところに、 彗星のふるさと、彗星の元になる天体が漂っている場所があると考えたのです。また、長周期彗星は宇宙の様々な方向から来るので、 そのような場所は、太陽を中心に球殻状に分布している事になります。このような長周期彗星のふるさとともいえる場所をオールトの雲と名付けました。 現在では、オールトの雲の半径は太陽を中心にして1〜10万天文単位だとされています。 10万天文単位はほぼ1.5光年になりますので、最も近い恒星(ケンタウルス座α星)までの距離の1/3にあたります。
ほぼ同じ頃、エッジワースが短周期彗星の遠日点の分布から、海王星の外側の黄道面上に小天体がたくさんあり、 そこから時々彗星がやってくるのではないかと提案しました。カイパーも、冥王星付近に多数ある小天体が、他の天体の引力で吹き飛ばされて、 オールトの雲になるのだと考えました。
ところで、木星から海王星の衛星の中には、多くの惑星や衛星の公転方向と反対方向に回っているものがあります。 このような衛星を逆行衛星といいます。その代表的なものは、海王星の衛星トリトンです。トリトンが反対方向に回っている説明として、 トリトン・冥王星は元々海王星の衛星であったが、ある時両者が接近しすぎ、冥王星がはじき飛ばされ、 トリトンが反対方向に回り始めたというものもありました(冥王星よりトリトンの方が大きい)。 ふつうに回っている衛星と逆行衛星が同時にできたとは考えにくいこと、逆行衛星の軌道は不安定ですぐに主惑星に落下するようになること、 逆行衛星が衛星群の外側にあることから、逆行衛星は海王星外側の小天体群から取り込まれたと考えるのが自然です。
それでは、惑星に取り込まれる途中の小天体はあるのでしょうか。このような天体は木星から海王星の間を公転していると考えられます。 実際に見つかったのが、小惑星キロンです。キロンは時々ガスを放出し明るく光り出すことがあります (バーストといいますその写真があります)。このようなガスの放出を続けていると、 何千万年かする内に放出するガスがなくなるはずです。ということは、何千万年も前からここにキロンがあったとすると放出するガスのはなく、 バーストできないので、最近ここにキロンがやってきたことになります。また、ガスの放出は太陽からの熱で起こるので、 太陽側からやってきたとは考えられません。となると、キロンは天王星より外側、おそらく海王星よりも外側からやってきたと考えられます。 その後の観測により、キロンのような、木星や土星より外側、海王星の内側を回る小惑星が多数見つかってきました。 これらの小惑星はその他の小惑星と区別してケンタウルス族(小惑星)と呼ばれています。ケンタウルス族の存在も、 海王星より外側に小惑星が多数存在することを予感させます。
海王星より外側を回る小天体がある場所はカイパーベルトとかエッジワースカイパーベルトと名付けられました。また、 後にそこにある天体を、(KBOまたはEKBO)とかTNO(Trans-Neptunian Object)と呼ばれるようになりました (日本では「えくぼ」と読めるのでEKBOがよく使われていました)。
キロンが見つかってから、さらに遠くの小惑星探しが行われるようになりましたがなかなかうまくいきませんでした。 1992QB1と番号のつけられた小惑星がEKBO発見第1号になリます。 その後も続々と発見され2005年はじめには1000個を超えました。
不思議なことに、1000個のうち200個あまりのEKBOの公転周期が、海王星の公転周期のちょうど1.5倍になります。 公転周期と公転半径の間に関係がありますので、これらの小惑星はほとんど同じ公転半径を持っていることになります。 その公転半径は約39天文単位です。これは冥王星の公転半径と全く同じです。このことは、 冥王星と同じような公転をしている小惑星がたくさんあることを示してます。冥王星と同じ公転周期を持つ小惑星(EKBO)を、 プルチーノ族と呼びます。
このこととは別に、 EKBOの中には、大きなものも見つかるようになってきました。半径が500kmを超えるものもたくさん見つかってきました。 大きさの記録も、バルナ、イクシオン、クアオアと更新され、次第に冥王星の大きさに迫ってきました。
2003年11月に発見されたセドナは、当初冥王星より大きいのではないかといわれました。現在その半径は1500kmとされ、 冥王星より小さいと考えられています。セドナについて注目しないといけないのはその軌道の位置です。 セドナ軌道は、太陽に最も近づいたときは76天文単位離れたときは900天文単位にもなります。この位置は、カイパーベルトよりも外側、 オールトの雲よりも内側になります。現在太陽に近づきつつあるときなので、発見できたけれども、太陽から離れた時は発見できないことが 考えられます。セドナの発見は、カイパーベルトの外側にも冥王星の大きさに迫る天体が多数あることを感じさせます。
このような発見が続いたことによって、冥王星はEKBOの中で大きな部類であると考える天文学者が増えてきました。 それに伴って、惑星とはどのようなものをいえばいいのかという議論がなされるようになってきました。
ほぼ同じ頃別の場所で撮影された写真に、さらに大きな小惑星が写っていることが2005年1月にわかりました。 最終的にエリスと名付けられたその小惑星の半径は約1200kmで、冥王星よりわずかに大きいことがわかりました。
エリスは、惑星なのかどうかが大きな問題となりました。2007年にあった国際天文学連合の総会でその扱いが議決されました。 結論を急ぐ前に再度太陽系内の天体を整理し、その形成過程を整理することにします。
惑星とは何かを調べる前に、太陽系にあるものを整理してみましょう。ざっと以下のものがあります。
| 1 | 太陽 | ほとんどの物質がここに集まっている | |||
| 2 | 太陽の周りを回っている天体 | ||||
| 惑星 | 水星・金星・地球・火星・木星・土星・天王星・海王星(・冥王星) | ||||
| 小惑星 | メインベルトの天体 セレスなど カイパーベルトの天体 キロン・バルナなど | ||||
| 彗星 | 細長い楕円軌道で、時々太陽に接近する ハレー彗星など | ||||
| 3 | 衛星 | 惑星の周りを回っている天体 月など | |||
| 4 | 宇宙塵 | 太陽の周りを漂っている微小粒子 流れ星のもととなる 黄道光や対日照として観測される | |||
| 5 | 太陽風 | 太陽から吹き出す荷電粒子の流れ | |||
ここで、小惑星は惑星でないものとして扱っています。また、「5太陽風」は目に見えるものではないことから、「4宇宙塵」も砂粒くらいの大きさで単独で観測にかからないので、 構成物としては無視されています。ただ最近の観測では小さな小惑星が見つかるようになり、宇宙塵と小惑星との間がだんだん狭まりつつあるようです。
惑星を分類するとき、よく使われているのが、地球型惑星・木星型惑星に分ける区分です。冥王星はこの区分表には所属できないとされていましたが、 似た天体が発見されてきたので、その特徴を加えた表にしてみました。構成物が似ているその他の天体も表に加え以下にまとめてみました。
| 項目\主成分 | 岩石でできている | ガスでできている | 氷でできている |
|---|---|---|---|
| 惑星の分類名 | 地球型惑星 | 木星型惑星※2 | 所属が不明とされてきた |
| 太陽からの位置 | 近い | 中間 | 遠い |
| 大型の天体 | 水星・金星・地球・火星 | 木星・土星・天王星・海王星 | 冥王星※1 |
| 中型の天体 | セレス | 引力でガスを引き留めておくことができないので存在できない | エリス・セドナ など |
| 小型の天体 | メインベルトの小惑星 | 太陽系外縁天体 (カイパーベルトの天体) | |
| その他の天体 | 月・フォボス・ディモス | テイタン・トリトンなど 彗星 | |
| 大気の組成 量 | 二酸化炭素・窒素・(水蒸気) 少ない |
水素・ヘリウム 多い | メタン?・窒素? 少ない |
| 自転速度 | 遅い | 速い | 不明 |
| 主成分 | 岩石 | ガス | 氷(水・メタン) |
| 密度 | 大 | 小 | 小 |
| 衛星数 | 0〜2 | 非常に多い | 0〜4? |
| その他 | 環を持つ | 公転面が大きく傾いている 軌道離心率が大きい | |
|
太線より下が、地球型惑星・木星型惑星の特徴として教科書に載っているもの。 ※1 中型の天体欄に入れるのが妥当、表を作るきっかけになったという意味でここに書いておく。 ※2 木星・土星を巨大ガス惑星、天王星・海王星を巨大氷惑星に分ける表もある。 天王星・海王星が巨大氷惑星なら※1の欄に入れるべきものか | |||
木星型惑星(巨大ガス惑星とも呼ばれる)は、岩石惑星や氷惑星が大きくなり、太陽系形成時の星間ガスを引力で吸収したできたものなので、 氷惑星・岩石惑星に分けた表の上に、巨大なものとして載せた方がいいのかもしれません。まとめてみると次のようになります。
| 構成物 | 気体 | ||
| 金属(鉄) | 岩石 | 氷 | |
| 惑星 | 太陽系には存在しない | 巨大ガス惑星 | |
| 地球型惑星 | (巨大)氷惑星 | ||
| 準惑星 | (セレスのみ) | 冥王星型天体 | |
| 小天体 | M型小惑星 | S型小惑星 | 外縁天体・彗星 |
| 衛星 | −−−−−−− | 月(地球) フォボス(火星) イオ(木星) | カリスト(木星) ティタン(土星) トリトン(海王星) |
 冥王星の所属を考える前にもう一つ、太陽系形成の過程で惑星がどのように生まれていったのかを考えてみる事にします。
冥王星の所属を考える前にもう一つ、太陽系形成の過程で惑星がどのように生まれていったのかを考えてみる事にします。太陽は何らかのきっかけで、宇宙空間にある星間ガスが収縮をしてできはじめたと考えられています。収縮のきっかけはおそらく超新星爆発で、 その爆風によってガスが圧縮を受け、濃度が高められたためでしょう。星間ガスは何カ所も濃度の高いところができ恒星に変わっていきますので、 周囲にいくつもの恒星ができはじめていたことでしょう。この様子は、オリオン星雲の写真の中にいくつかできかけの恒星があることからわかります。 (オリオン星雲はNASAのホームページhttp://amazing-space.stsci.edu/news/archive/2006/01/photo-02.phpで見られます。 右図はそこから恒星形成領域の一部を抜き出したものです。)
収縮を始めたガスは回転し始めます。球形からだんだん平べったくなっていき円盤形になります。このガスの円盤を、原始惑星系円盤といいます。 温度は回転中心に近いほどたくさん圧縮されるので高温になります。円盤の回転面上(中心を通る回転軸に垂直な面)には、 ガスに含まれていた固体粒子(塵)が集まってきます。中心に近いところには鉄だけが、離れると岩石や氷の粒が入ってくるようになります。
塵の層では、粒が衝突合体を繰り返して大きくなっていきますが、次第に塵の層に濃度の濃いところや薄いところができてきます。 濃度の濃いところでは引力が働き、塵が集まって直径数km程度の大きさのかたまりができます。このかたまりを微惑星といいます。
微惑星ができてからしばらくすると、お互いの引力で軌道が乱されるようになり衝突・合体をはじめます。初めのうちは、 引力で周りの微惑星を集めて急速に大きくなりますが、直径数千km位になるといったん成長は止まります。この大きさまで成長したのが原始惑星です。 原始惑星は数十個できていたと考えられています。
数十個の原始惑星は、その後、衝突合体を繰り返し、最終的に数個の惑星になります。この時特に大きくなった木星・土星は重力によって、 周囲にあった水素・ヘリウムを主体とするガスを引き寄せてさらに大きくなります。ガスは、現在の太陽系では散逸してしまって見ることはできません。
以上が太陽系生成について考えられているシナリオです。木星・土星がどのようにしてガスを引き寄せられる大きさにまで急速に成長したのか、 ガスはどのようにしてなくなっていったのかなどわからない点も多数残されています。
太陽以外に惑星を持っているものがあるのではないかという疑問は当然です。太陽系以外の惑星ということで系外惑星と呼ぶことにします。 恒星の周りを回っているものは系外惑星以外にもあります。系外惑星を探す前にそのことについて触れておくことにします。
恒星を調べてみると、意外に連星系を形成しているものがたくさんあります。連星というのは、 2つ以上の恒星が互いにその共通重心を中心に回っているものです。2重星・3重星というのは恒星が重なって見えているものです。 たまたまその方向にあるも指しますが、その中の大部分は連星であるといわれています。
連星で、一方の星が小さいことは知られていますが、もっと小さくなるとどうなるのでしょうか。集まるガスの量が少なくなると、 中心部で核融合反応が起こらず自分の力で光ることができなくなります。このような星は褐色矮星と呼ばれています。 これは恒星ではありませんが、惑星ともちがいます。なぜなら、木星のような惑星が大きくなり過ぎ、核融合反応を起こし始めたものではないからです。 前章の、惑星形成論によると、木星程度の大きさに惑星が成長すると、その引力のため周囲のガスさえも吹き飛ばされると考えられているからです。 逆に、連星は、宇宙空間のガスが収縮するときに乱流が生じ、ガスの収縮の中心が2カ所以上できた場合に作られます。 この時、木星質量の40倍以上のものができますので、褐色矮星の大きさの下限はこの大きさになります。 これに対して、惑星の大きさの上限は木星質量の20倍程度だといわれています。系外惑星探しは、その質量も重要になってきます。
最近になって発見されだした系外惑星はどんなものがあるのでしょうか。系外惑星の見つけ方は大きく3つの方法があるようです。 一つ目は惑星によって恒星がふらつく大きさを捕まえるもの、二つめはふらつく勢いをつかまえるもの、三つ目は恒星を惑星が隠す様子を捕まえるものです。 いずれにしても、恒星をふらつかせたりするのですから、惑星は大きいものになります。また、勢いも強い方がわかりやすいので速く動いているものが、 言い換えれば、恒星の近くをかすめるように動くものが発見しやすくなります。実際に最初に見つかった系外惑星は、 地球の公転半径の1/10以下の半径で回っている木星ほどの質量を持つ天体でした。その後、似たような大きさや軌道半径を持つものが多数見つかりました。 これらの天体は、木星に似ているが、恒星に近い灼熱の場所を回っている事から「ホットジュピター」と呼ばれています。二番目にに見つかったものは、 恒星のそばをかすめるように通り、遠ざかっていく木星程度の質量を持つ天体です。このような特徴を持ったものも多数発見され「エキセントリックプラネット」 と呼ばれています。これらの天体は、太陽系の惑星と比べると異様なものですが、惑星といえるでしょう。ホットジュピターは、巨大惑星形成後、 ガスとの摩擦で中心の恒星の近くまで落ち込んだもの、エキセントリックプラネットは、いくつかの巨大惑星の重力作用で軌道がいがめられたもの と考えられます。系外惑星は、巨大なものばかりですが、観測精度の向上によってより小さなものやゆっくり回るものも検出できるようになってきています。 最近では、地球の質量の3倍程度の大きさのものが検出できたという報告があります。
2006年8月IAU総会での決議で太陽の周りを回る天体を次の3つに分類すると決められました。
1.大きくなったために、周囲の天体をどかしてしまったものを惑星と呼ぶ
2.自分の重力で丸くなっているもののうち惑星以外をDwarf Planetと呼ぶ
3.それ以外の小天体をSmall Soler System Bodiesと呼ぶ
2.自分の重力で丸くなっているもののうち惑星以外をDwarf Planetと呼ぶ
3.それ以外の小天体をSmall Soler System Bodiesと呼ぶ
これ以外にも、海王星より外側を回っているSmall Soler System BodiesをTrans Neptune Object(TNO)と呼ぶ事も決まりました。 この決議によって、冥王星は惑星の座から正式にはずされ、Dwarf Planetの仲間となりました。従って、太陽系の惑星の数は8個になりました。
日本学術会議は翌年4月9日に 「国際天文学連合における惑星の定義及び関連事項の取り扱いについて」と題した報告でこの取り扱いをまとめています。 日本語の名称については、
「Dwarf Planet」 日本語表記が必要な場合は「準惑星」
TNO 「太陽系外縁天体」太陽系とわかれば外縁天体でもよい
Small Soler System Bodies 「太陽系小天体」とするが使用には注意が必要
と書かれています。TNO 「太陽系外縁天体」太陽系とわかれば外縁天体でもよい
Small Soler System Bodies 「太陽系小天体」とするが使用には注意が必要
基本的に、惑星の定義も含めて冥王星の位置づけにはIAUの決議に賛同しているものの、いくつかの点で問題点があるとも指摘しています。 なかでも「Dwarf Planet」は、IAUに再検討するよう要望するとまで書かれています。準惑星についての問題は別に取り上げることにします。
惑星の定義を考える前に、どのように定義を定めていけばよいのかについて検討してみます。参考になるのは生物の分類法です。 はじめは形態が似ているものを同じグループにすることから始まりましたが、進化の過程が近いものを同じグループにする方法がとられています。 この方法を使うと、例えば「ほ乳類」は「は虫類」の中で胎生を獲得したグループ、というように段階を表した分け方にもなります。
この観点から惑星を定義するとどうなるのでしょうか。原始惑星の段階まで成長したグループとするのが妥当だと考えられます。 この段階まで成長したとき、周囲の微惑星を吸収したりはじき飛ばしたりして原始惑星以外のものが周囲から一掃されいると考えられます。 従って、惑星の定義として「周囲の天体をどかしてしまったもの」というのは妥当だと考えられます。
もう一つ、考えておかないといけないのは、将来予想外の系外惑星が発見されても定義の適用に困ることがないように考えておくことです。 おそらく大きさの下限は検出の限界値付近と思われるので、問題は起こりそうにもありませんが、上限については再考が必要です。 自分の力で光らないものと定義されていますが、これでは褐色矮星が含まれてしまいます。原始惑星系星雲から形成されたものにする必要があります。 実質上は木星質量の10倍(安全を見て20倍)以内がいいのではないでしょうか。最もIAUの定義は「太陽系」とわざわざ断っていますから、 別に問題は発生しないようです。実際問題として、周囲に天体がない事を証明するのは難しいように思われす。
最後に質問です。エキセントリックプラネット形成の過程で、木星サイズの惑星が恒星の重力圏の外にはじき飛ばされることがあります。 現在の太陽系でも、約50億年後太陽が燃え尽きる過程で、木星〜海王星の軌道が不安定になり、いずれかの惑星が宇宙空間に掘り投げられる可能性も指摘されています。 このようにしてできた、宇宙空間を放浪する元惑星は何と呼べばいいのでしょうか。
日本学術会議は次の2つの点で準惑星の定義に問題があると指摘しています。一つは、全く形成過程の違う天体が同じグループに入っていること、 もう一つは大きさの基準である丸くなっていることがあいまいな概念であることです。これらについて詳しく見ていくことにします。
全く形成過程の違う天体が同じグループに入っている問題
現在準惑星とされているものは、セレス・冥王星・エリスの3つです。準惑星になる可能性のあるものとしては、クワオアやセドナなどがあげられます。 このうちセレスは、メインベルト(小惑星帯)の小惑星と同様、原始惑星が衝突破壊されてできた破片であると考えられます。これに対して、 その他の、準惑星及びその候補たちは、外縁天体であり、かってはEKBO(セドナはオールトの雲とする考えもある)の一員でした。 このような領域にある天体は、微惑星が集積し大きくなっていったのだけれども、原始惑星にまで大きくなれなかったものだと考えられています。 もちろん、セレスは原始惑星にまで成長しきれなかった微惑星である可能性がないわけではないのですが、周囲にある小惑星のほとんどが、 より大きな天体の破片であることを考えてみると、セレスも破壊から逃れられることはできなかったはずなので、破片であると考えるのが妥当です。 メインベルトの天体が元々大きな天体であったことは、地球に落下してきた隕石が、高温・高圧の場所でできる構造を持っていることから推定されています。 逆に、外縁天体が、破壊によってできたものでないという決定的な証拠もありません。惑星形成理論から、 この付近では原始惑星にまで成長するのに必要な時間が足りないという問題、衝突速度がそれほど大きくならないといったことから、 破壊されてできたた破片ではないと考えられます。
天体の形成過程が違うということなのですが、構成物の違いもはっきりしています。一方は岩石(・金属)、他方は氷でできているということです。 ただこの問題に関しては、準惑星の概念が持ち出される以前からありました。惑星の分類表を見ると明らかです。 EKBOとそれ以外(メインベルトの小惑星、このようには呼んでなかった)とは区別してしていたものの一括して小惑星として扱われていました。 別のものに分けて考える必要が生じていたわけです。それを一緒にしたのは失敗です。この内の冥王星類似の天体について、 plutonian objectを提唱しようとしましたが否決されました。しばらくして、plutoid(こちらは準惑星のみ)にすると2008年6月に決まりましたが、 言葉の違いがよくわかりませんし、片方だけに名前をつけるのはいいことはいえないでしょう。セレスがひとつだけ取り残されてしまいました。
大きさの基準があいまいな概念であるという問題
準惑星の定義が持つ二つめの問題点について考えてみますが、その前になぜ地球は丸いのかという問題に答えることにします。 目の前に豆腐があると思ってください。これを4つほど積み上げるとどうなるでしょうか。おそらく、一番下の豆腐は上の豆腐の重みで押しつぶされ、 壊れてぺっちゃんこになるでしょう。豆腐は4つ分の高さ20cm位より高く積み上げる事はできません。つまり、地球の表面が豆腐でできているとすると、 20cm以上高い山はできないことになります。つぶれた豆腐は重力と垂直な方向に広がっていきます。広がっていく方向が作る面は、 自転していなければ球形です。従って、表面が豆腐でできた地球の形は表面に20cm程度のでこぼこはできるものの球形になるわけです。 実際の地球の表面は岩石でできていますので、豆腐とは違うように感じるかもしれませんが、高く積み上げると下の方の岩石がつぶれることは同じです。 10kmも積み上げられないでしょう。準惑星の定義で大きさの下限になっている「自重が剛性力に打ち勝つ(self-gravity to overcome rigid body forces)」 とはこのことです。多少表面にでこぼこはできますがつぶれて球形に近くなります。でこぼこの大きさは、人間ピラミッドを作るときのように上の方ほど量を少なくすると、 もっと高くまで積み上げることができ、大きなふくらみを作ることができます。このことを加味しても、地球表面には最大で数十kmのでこぼこはできますが、 数十kmは地球の半径に比べて100分の1程度ですので、ほとんどわかりません。地球の形は球形と言っていいでしょう。 地球の場合はこれとは別にアイソスタシーといって表面を平らにしようとする働きがありますので高低差は20kmと小さくなっています。
丸くなる事を説明しようとしたのですが、丸くなろうとすることしか説明できていません。その結果が丸いと認識される形になっているに過ぎません。
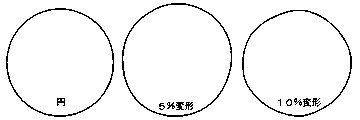 実際にはどうしても表面にでこぼこが残されます。どの程度のでこぼこまで許容されるのでしょうか。半径の10%でしょうか。
これは手だけで円を描いてみてうまくできたと思ったものにあるでこぼこの大きさです。右の図の左端は円、真ん中は円から半径の±2.5%の範囲内を通る図形、
右は±5%の範囲内を通る図形です。円を横に並べてみると少し変形しているのがわかりますが、単独では円らしく見えます。
±5%では少しいびつな感じもします。これででこぼこの割合いが10%になります。とりあえずこの程度のでこぼこが許されると考えてみましょう。
まず最初に、地球の場合20kmのでこぼこがあります(とします)。これは半径6400kmの320分の1です。半径が半分の3200kmになると20kmは半径の160分の1ですが、
表面の重力加速度は半径に比例するため半分になりますから、岩石を2倍の高さまで積み上げることが可能となり、でこぼこと半径の比は80分の1になります。
さらに半分の大きさと計算していって比が10分の1になる大きさを求めると半径約1000kmとなり、ほぼ冥王星の大きさになります。
実際には、さらに半分の大きさのセレスが準惑星とされています。どの程度まで変形していても丸いとするのか興味のあるところです。
セレスが球形かどうかはNASAのホームページの写真で確認してください。
実際にはどうしても表面にでこぼこが残されます。どの程度のでこぼこまで許容されるのでしょうか。半径の10%でしょうか。
これは手だけで円を描いてみてうまくできたと思ったものにあるでこぼこの大きさです。右の図の左端は円、真ん中は円から半径の±2.5%の範囲内を通る図形、
右は±5%の範囲内を通る図形です。円を横に並べてみると少し変形しているのがわかりますが、単独では円らしく見えます。
±5%では少しいびつな感じもします。これででこぼこの割合いが10%になります。とりあえずこの程度のでこぼこが許されると考えてみましょう。
まず最初に、地球の場合20kmのでこぼこがあります(とします)。これは半径6400kmの320分の1です。半径が半分の3200kmになると20kmは半径の160分の1ですが、
表面の重力加速度は半径に比例するため半分になりますから、岩石を2倍の高さまで積み上げることが可能となり、でこぼこと半径の比は80分の1になります。
さらに半分の大きさと計算していって比が10分の1になる大きさを求めると半径約1000kmとなり、ほぼ冥王星の大きさになります。
実際には、さらに半分の大きさのセレスが準惑星とされています。どの程度まで変形していても丸いとするのか興味のあるところです。
セレスが球形かどうかはNASAのホームページの写真で確認してください。丸くなろうとする力は、構成物質の性質によっても違ってきます。密度が小さいと、自重や引力が小さくなるので、丸くなりにくくなります。 これとは別にに岩石に比べて氷は変形しやすいので、はやく丸くなろうとします。地球上で氷に覆われている南極大陸の表面は平坦です。 現在も氷は流れて平坦になろうとしています。南極大陸の平均高度は約2kmです。この半分の1kmの高さが氷にとって安定できる高さだとして考えてみます。 地球が氷だけでできているとすると表面重力は5分の1になりますので、この時の安定な高さは5km、地球を小さくしていき高さと半径の比が1:10になる半径は、 岩石の時の半分の500kmとなります。このように、岩石天体と氷天体では丸くなれる最小の大きさが異なります。中心に岩石があって表面が氷で覆われていると、 丸くなれる半径はもっと小さくなります。もっと極端な場合、液体でできている天体、かっては液体が表面を覆っていたけれども現在は固化している天体はどうでしょう。 例えば、創世記の地球表面の岩石は溶けてマグマオーシャンを形成していたと考えられます。この時の状態を考えてみてください。 液体の表面は水平になりますので、この天体は完璧な球形といっていいでしょう。どんなに小さくても球形の小惑星ができます。 マグマオーシャンに隕石が落下し飛び散ったしぶきからできた天体はおそらく球形になるでしょう。これを準惑星と言っていいのでしょうか。 液体でできた天体を想定していないので答えはNOですが、これが半径500kmくらいだったらどうでしょう。 氷は地球上部マントルの物質と同様、固体であるけれども流動する液体の性質も持っています。従って、固体でよくて液体ではだめというな基準はいかがなものでしょう。
準惑星を太陽系小天体から区別できるのか
日本学術会議は準惑星の大きさの基準を、たとえば直径1000km以上(セレスは準惑星でなくなる)にする事を提案しています。 準惑星の提案から可決まで1ヶ月もかかっていません。準惑星の概念が必要かどうかも含めて慎重に審議されてもよかったのではないでしょうか。 太陽系外縁からはこれからも多数の天体が発見されるでしょう。その中には様々な形や大きさをしたものが連続的に見いだされるでしょう。 また、より遠くの天体が発見されにつれ、その大きさや形の決定するには難しくなっていくでしょう。このようなことを考えてみると、 新しく発見された天体が準惑星に属するか太陽系小天体に属するかを判定しようとしたとき、どれを境界にしようか判断に迷うものが出てくることは多分に想像できます。
準惑星が定義されてから、ほぼ2年が過ぎようとしています。定義を決めたときに、セドナやクアオアなどいくつかの天体が準惑星になるかもしれないとされました。 その内の一つマケマケが準惑星であるという結論がやっと出ました。この天体の正式名称がなかなか決まらなかったこともありますが、 準惑星かどうかの結論がなかなかだせないこと自体にも定義が抱えている問題が現れていると思われます。
太陽系の大きさ
IAUが、惑星の定義を決定しようとしたきっかけは、冥王星付近やそれより遠くを公転している天体についての情報が集まりだしたことにあります。 そして、冥王星は他の惑星たちと大きく異なっていて、新しく発見された天体たちと同じ仲間であることがわかりました。 その結果として、冥王星の仲間たちの集団を考えようということになりました。これがTNO(太陽系外縁天体、直訳は海王星以遠天体)です。 太陽系の世界が大きく広がったのです。
かってTNOはEKBOと同じ意味で使用されていました。日本人としてはEKBOが採用されて欲しいという願望はあるものの、 欧米で主流だったTNOが採用されました。EKBOの範囲は太陽からおおよそ50天文単位、 さらに外側にあることがわかっている散乱円盤と呼ばれる区域まで含めると100天文単位までの領域が明らかにされてきました。 おおよそこの範囲で新しい天体が発見されたことになります。太陽系で捜査可能な範囲は約2倍に広がったことになります。
ところで、太陽系の外側にはオールトの雲が広がっていると推定されています。その半径は5〜15万天文単位で、 新しくわかった領域のさらに500〜1500倍外側の世界です。オールトの雲と散乱円盤が連続してつながっているのではないかという推定もあることもあわせてみると、 太陽系領域の中でわかっている場所というのはほんのわずかであることに気がつきます。
さらに観測技術が進歩して、より外側の領域の情報がわかるにつれ、TNOという用語が変化していく可能性はじゅうぶんに考えられます。 かってこの領域はEKBO・散乱円盤・内オールトの雲・外オールトの雲と分けられていて、性質の違うものだと考えられていました。 一つにまとめないといけない理由はありません。といって分けようとした時、境界がはっきりしていて簡単にできるというわけでもありません。
衛星の定義についての問題
IAUが新しい惑星の定義を提案しようとしたとき、新たな惑星候補の中に冥王星の衛星であるカロンが入っていました。 衛星でなく惑星であるとしたのはどうしてなのでしょうか。それは、冥王星に対してカロンの質量が大きいことにあります。カロンが衛星ではないとして、 何にしたらよいのかを考えてみましょう。順番に次のように考えが進んでいくでしょう。 カロンは冥王星と対になっているから小惑星とはいえない→冥王星と二重惑星になっている→カロンは惑星である→カロンより大きな小惑星たちも惑星 =他の小惑星とどこが違うか→カロンは球形である→自重で球形になっているものを惑星としよう、というところでしょうか。
ところで衛星が大きいとどのような事が起こるのでしょうか。とりあえず、中心の天体を主星と呼ぶことにします。衛星が極端に大きくて、主星と同じ質量ならどうでしょうか。 この場合どちらが主星かはっきりしません。相手の星を振り回そうとしたら、相手の星からも振り回されます。二つは同じ大きさなので、 二つの星のちょうど真ん中を中心に、二つの星が互いに反対の位置になるように回転します。どう見ても主星の周りを回っているように見えません。 どちらの星も相手の星の周りを回っているように見えないので、このような場合は二重惑星となります。衛星側が少し軽い場合はどうなるのでしょうか。 相手の星によって振り回される大きさは、相手の星の質量に比例します。二つの大きさが釣り合うのは、2星間距離を相手の質量で比例配分した位置になります。 ここを共通重心といい、ここを中心にして二つの星が回っているように見えます。
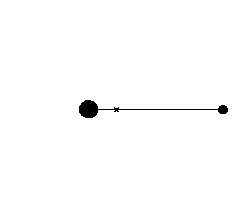 冥王星とカロンの関係は右のようになります。大きい方の黒丸が冥王星で、×印が共通重心になります。カロンの質量は冥王星の約4分の1なので、
冥王星の回転半径は、カロンの約4分の1になっています。これくらいでも、冥王星がカロンに振り回されている様子がわかります。
カロンの回転の中心が冥王星にあると言っていいのか微妙な位置にあります。つまり二重惑星といってもよいと思われます。
冥王星とカロンの関係は右のようになります。大きい方の黒丸が冥王星で、×印が共通重心になります。カロンの質量は冥王星の約4分の1なので、
冥王星の回転半径は、カロンの約4分の1になっています。これくらいでも、冥王星がカロンに振り回されている様子がわかります。
カロンの回転の中心が冥王星にあると言っていいのか微妙な位置にあります。つまり二重惑星といってもよいと思われます。それでは、主星と衛星とに区別できるのはどこでしょうか。IAUは、共通重心が主星の内側にある場合に相手の星を衛星にしようと考えました。 結局、別の議論が白熱したため、衛星の定義をどうするかという議論はなされないまま終わりました。IAUの提案が妥当かどうか考えて見ます。
この基準では、冥王星−カロンの関係は、主星−衛星の関係ではないことになります。地球−月の関係はどうなるのでしょうか。 月の公転半径は約38万kmで、質量は地球の約81分の1ですから、この二つの数値をかけた約4700kmが地球から共通重心までの距離になります。 この値は地球の半径6400kmより小さいので、共通重心は地球内部にあり、月は衛星ということになります。でもよく見ると、 共通重心は地表から1700kmのところにあります。これは、地球内部に4分の1ほど入ったところで、下部マントルにあたります。 意外と地球も月に振り回されている感じがします。ところで、月は地球からだんだん遠ざかっています。そのため公転周期が次第に遅くなり40日くらいになるともいわれています。 この数値で計算してみると、共通重心は地表から約700km下の、最も深い地震が発生しているあたりになります。したがって、月は永遠に地球の衛星ということになります。 でも、月が52万km(6400×82)より遠くにあったとしたら衛星ではないことになります。公転半径によって衛星かどうか変わるのはいかがなものでしょうか。
別の例をあげてみます。太陽と木星の関係を考えてみてください。この二つの星の共通重心はどこにあるでしょうか。計算すると微妙な位置になりますが、 共通重心はわずかに太陽の表面の外側になります。もちろん、木星は衛星ではなく惑星です。しかし、太陽の周りを回っているといってよいかどうかという問題点では共通しています。 木星が惑星であるなら、衛星でないとするためには共通重心が惑星(準惑星を含む)の外側にあるという理由だけでは、妥当であるとはいえないでしょう。
分類方法の統一と拡張
IAU2007年の決定によって新しい分類基準が決定されたことになります。この基準と、他の分類基準と比較することにします。 よく見ると、生物・岩石・鉱物・化学物質などに一般的に使われている分類方法と、太陽系天体の分類方法に何点か大きな違いがあることがわかります。
一つは、一般的な方法では全体をいくつかの群に分けそれぞれに名前をつけ、それをさらにいくつかの群に分けて名前をつけということを繰り返して、 最終的に個々の物にたどり着くことができるようになっています。ところが太陽系天体ではそのようになっていません。 例えば5章6章で書かれた分類群には名前のついていない物が多数あります。さらに、IAU2008年の決定では、準惑星の内冥王星のようなものを「プルトイド(冥王星型天体)」 とましたが、これに対するセレスの仲間(一つしかないが)には名前をつけない事を決めました。同じ様なことですが、二つに分けた小天体のうち、外縁天体でない物には名前がありません。 アステロイド(それのある場所をメインベルト)という名前があるのかもしれませんが、はっきりとその定義が宣言されていません。
二つめは、一般的な物の分類方法では、それの形成過程を重視しているのに対して、太陽系天体ではそれほど考慮されていません。 これは、日本学術会議が準惑星の定義に関して述べているとおりですが、それ以外にも何点か見受けられます。
三つ目は、ある分類群で細分に重要だった項目が別の分類群にもあった場合、そこでも同等に扱われているかいないかということです。 たとえば、自重で丸くなっているという項目は、太陽周回天体(とここでは呼ぶことにする)では重要な事項ですが、衛星では無視されています。
一般的な分類方法が作られた初期の頃は、見つかった物に名前をつけ、それをいくつかの群に分けていく事が中心でした。 太陽系天体については、まだその段階なのかもしれません。9章で述べたような別の恒星系のことも視野に入れ新しい分類基準ができていくことを期待しています。
ところで、このような分類基準の不統一性から、冥王星を別格にしたいとする意図を感じるのは私だけでしょうか。
惑星Xはあるか
太陽系にあるかもしれない未知の惑星を、惑星Xと呼ぶことがあります。Xは、冥王星が惑星の仲間に入れられていた頃には10番目のという意味も込められていました。 海王星以遠には冥王星の大きさに匹敵する外縁天体が続々と発見されてきいます。その中で、エリスは一時冥王星より大きなため第10番目の惑星の候補とされました。 その後の惑星定義の決定によって、冥王星とともに惑星には含めないことになりました。そして次に発見される惑星の番号は改めて9番目になりますから、 10番目のという意味はなくなってしまいましたが、未知の惑星という意味で「惑星X」という用語は使われています。
2008年2月に、一つの論文が発表されました。それは、冥王星以遠に地球よりやや小さな惑星(天体)がある可能性を示すものです。具体的には、 それがあることによって、外縁天体の軌道の形や傾きの謎が説明できると述べています。それでは、この天体は、惑星といえるのでしょうか。 他の天体の軌道を散乱させているところから、惑星のようにも思えますが、自分自身も大きく振り飛ばされているので、他の天体を一掃するという新しい惑星の定義からは、 遠いようです。
もっとも、この理論自体、地球程度の天体があるという仮定の元に組み立てられていますので、惑星を考えない他の仮定で、 現在の現象が説明できないと証明されたわけではありません。惑星がないといけないということではないので、論文の発表によって新惑星発見の可能性が高まったというようにはいきません。 ただ、新惑星捜索の範囲を広げないといけない事だけははっきりさせてくれました。
太陽系形成理論によると、海王星以遠の領域では、微惑星が集積し原始惑星にまで成長するための時間が足りなかったようです。冥王星のような、原始惑星への成長段階を示す天体は、 今後も多数発見されるでしょう。それは、最も外側を回っているセドナ(2006年に発見された天体はさらに1.5倍外側を回っていることがわかった)が発見されたときに想像されました。
それは、セドナが観測できるのは、太陽に近づいたほんの一時期だけだからです。新たに発見される天体は、冥王星・エリスや外縁天体だったかもしれないトリトンより大きな可能性はじゅうぶんに考えられます。 しかし、それが地球ほどの大きさになっているかの可能性は少なく、さらにそれが新しい惑星の定義にあう可能性はさらに小さいでしょう。
<参考になる文献>
| 最新太陽系論 | 矢沢サイエンスオフィス編集 | 学研 最新科学論シリーズ10 |
| 太陽系の果てを探る | 渡部潤一・布施哲治著 | 東京大学出版会 |
| 異形の惑星 | 井田茂 | NHKブックス |
| 惑星学が解いた宇宙の謎 | 井田茂 | 洋泉社新書 |
ヨッシンと地学の散歩