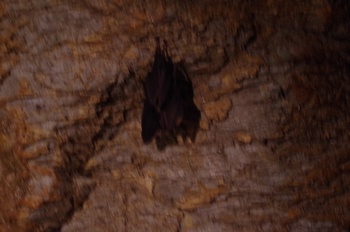2016/04/08-09 中国山地へそ巡り
01 計画そして出発
望遠鏡を担いで星を見がてら、旅行に行きたくなりました。4月だと冬の星座がまだ見ることができます。いくつかの天体にあと一息でたどり着くところまでいっています。なんとか、観測に成功したいものです。それと春先といえば、夕方の黄道光が見やすい時期です。あわせて観測したいものです。
いつ行くのかとなると、やはり新月前後です。4月7日が新月になっています。この前後ということになります。場所も問題です。いつも通り、公共の宿を探していると星がきれいにみえると書かれているところがありました。問題は、7日までは休館していて8日から宿泊ができるようになります。ちょっと遠いのですが、他を当たるのが面倒なのと、これより近くで条件の良さそうなところを見けられなさそうだったので、ここに泊まることにします。場所は、中国山地吾妻山の近くの標高1000mの所になります。
9日出発にすると、往復とも高速道路が3割引になります。元々が高いので、この割引は魅力です。1日遅れただけではそれほど影響がありません。宿の方が、割高になるので、帰りだけこの割引を利用することにしました。あとで気が付いたのですが、1日遅らせると往復と渋滞にかかっていたかも知れません。行きはできるだけ手前で降りて、高速料金を浮かせることにします。
どこに立ち寄るかを考えないといけません。このあたりは、一度通っています。前に来たところを避けてみると、地図上に書かれているものに特にこれはと言うものはありません。強いていえば、出雲街道の宿場町が残されているところがいくつかあるくらいです。とりあえず、立ち寄ったところの道の駅などで情報を収集しながら進んで行くことにします。
これで、日程は4月8日から1泊2日で、行き先は中国山地中央部というように決まりました
8日の朝です。中国道は宝塚トンネル付近で渋滞するのでできるだけ早く出発したいものです。いつもより早めに起きたものの、荷物を積み込んだりしているとちょっと遅くなりました。結局、宝塚での渋滞が始まっていました。まだそれほど長くなっていなかったので、20分ほどで抜けることができました。途中は特に混んでいるということはなかったのですが、一台だけ前に割り込んではゆっくり走るという車に遭遇しました。仕方なく追い越したら、追い越し返して前をゆっくり走るのを何回も繰り返しで少しいらっとしました。集中力が切れかけていたのか、気が緩むとこちらの速度が遅くなっていたのもあったのかも知れません。その車は下り坂が速かったのでそこで先に行ってもらい、しばらくゆっくり走ることにしたこともあり離れていきました。
車のこともあったので、勝央のSAで休憩を入れ、どこによるか情報を入手することにします。トイレに行きたくなっていたのもあります。
SAでは、ツバメが巣作りの最中でした。何カ所かで作っています。見ていると巣材を咥えて、つける順番を持っているものもいます。
桜の花が咲いていますが、だいぶ散りはじめています。
ミツバツツジが咲いています。もう春本番なのですね。
SAで、見つけた情報はいくつかあります。高速道路より南側は前回行っているので、北側を中心に見ると、興味を引いたのは鏡野町大地区にカタクリの自生地があることです。醍醐桜・岩井畝の大桜が満開に近い状態だそうです。出雲街道の町並みは、勝山町と新庄町で保存されています。
まず、カタクリの自生地に行ってそこから勝山町並みを見てから神庭の滝に行き、大桜を見てから新見に抜け、周りの様子を見ながら庄原まで行くことにします。
高速道路は、この先落合JCTから米子自動車道に入り、最初の久世ICで降りることになります。
折りたたむ
久世ICで降りて、鏡野町大地区のカタクリ自生地に向かいます。料金はETCカードのポイント還元で安くなっているはずなのに、高めでした。帰ってから調べたら、まだ還元分は引かれていませんでした。ここからの道は、SAで場所の書いてある地図に従っていくことにします。地図ではいったん国道に出て、島根方面に向かい川を渡ったところで右折し山の中の方に向かうことになっています。その後は高速道路をくぐったあたりにある三叉路で左折して高速道路沿いに進み、久世から来る道に突き当たったところで右折してさらに高速道路沿いに進みます。最後がよく分からないのですが、二股に分かれた道のちょうど真ん中に印が振られています。このあたりは何とかなるだろうということにして進みます。
走ってみた感じでは、だいぶ地図と違うようです。カーナビも周りの様子が分からない細かい地図にしないと道路が標示されません。
行き当たりばったりで行くしかないようです。途中2ヵ所ほどに標識があったので、近くまでは来られたようです。駐車場を示した看板を見つけ狭い路地のような道を駐車場を探しながら進んで行くとちょっと広い道に出ました。どちらかなと標識を探すと、今来た道の方向を指しています。このあたりで車を駐められるところがないので、Uターンして戻るとすぐに駐車場がありました。最初に来た方向からの標識がなく、そちらから見えたところは個人の駐車場のようだったので見逃したようです。
駐車場には先客が一台ありました。車から降りて足元を見るとツクシがまだ残っていました。スギナもだいぶ伸びてきています。
駐車場の場所は、古い民家があって別の場所に移築した跡地のようです。物置小屋のようなものが残っています。キケマンの花が咲いていますが、元の庭に植えられていたものでしょうか。
駐車場の奥の方に進んで行った先にある斜面が自生地のようです。休憩所のような広場の桜は、ちょうど満開のようです。
斜面のカタクリです。比較的密度が多いようです。
花をアップで撮ってみました。
カタクリに混じって、ショウジョウバカマも咲いています。
こちらは、ニリンソウです。ピンクがちょっと混じっているのがきれいです。カタクリに混じって咲いていました。
カタクリの花を一通り見て、写真を何枚か撮ったので次に向かうことにします。駐車場に戻ろうとしたら、道でシマヘビがどくろを撒いていました。胴体が多いと思っていたら、よく見るとムスカリの花を挟んで頭が2つあります。2匹いたのですね。退いてくれないと駐車場には戻れません。
へびをちょっと脅かしたら、穴の中に戻ってもらうことができました。車に戻って元来た道を引き返します。途中、高速道路をくぐるところで。滝があるという標識を見つけました。寄っていくことにします。道は谷に沿って進みます。畑の横には、ミツマタがたくさんあるところがあります。花は、ちょうど満開のようです。
休憩所のような建物から入ったところに滝があるようです。駐車場はありませんが、このあたりの道幅は広いので道路脇に駐めて見に行きます。道路脇の桜も満開のようです。
足尾の滝といいます。本流ではない割には、水量は多いようです。本流は道沿いに流れています。
滝の入口には立派な鳥居があって、足尾神社と書かれています。滝の正面にあったのは小さな祠だけでした。アンバランスな感じがします。
次に向かうことにします。葉っぱのいっぱい被った道を3回ほど切り返して車の向きを変え、来た道を引き返していきます。次は勝山の町に行きます。
折りたたむ
足尾の滝から中国勝山へは、来た道を引き返し、途中から久世の方に曲がり、国道に出たところで、出雲の方に走っていくことになります。
久世の町に入り、国道に出たところで右側に明治時代風の小学校の建物が見えます。見学できるか分からなかったのと、交通量が多く車を駐められる場所を探している余裕はなかったのとで見るのはあきらめました。後で調べてみると、明治時代に建てられた旧遷喬尋常小学校でこのあたりの観光名所になっているようです。他にもよく見ると、この近くにトンネル桜とか見所はいっぱいあったようです。パンフには、土産物屋と食べ物屋しか書かれていないような気がしたので、じっくり見ていませんでした。よく見ておくべきでした。
そのまま国道を10分も走らないうちに勝山に到着します。駅に観光案内所と駐車場があるみたいなのでよっていきます。観光駐車場というのがあるのですが、地元ナンバーの車でいっぱいで駐めるところがありません。車をターンさせていると、1台出て行ったのでその場所に駐めます。それでも枠外駐車になっています。案内所ではガイドマップが手に入りました。これからどうするかを考えます。ここの駐車場は枠外なので、移動させることにします。町並み保存地区近くの、木材ふれあい会館に駐車場があります。ここに駐めて、そこから歩いてまわることにします。
木材ふれあい会館は、木材市場のとなりにあります。加工品や化粧木材が売られています。入口脇に、蒜山の近くで10年ほど前に倒れた、樹齢300年ほどの杉の木が展示されています。年輪にいつ頃のもの書かれています。見ると天明や天保の飢饉の頃の年輪が詰まっていたりと、気候変動との関係がよく分かります。
ふれあい会館から川を渡って反対側が町並み保存地区になります。城下町だったようです、向こう側に城山があります。2つ並んだ手前側は太鼓山で、向こう側が本丸のあった如意山です。山の麓の、家が並んでいるところが、旧出雲街道です。
橋を渡って川沿いに、高瀬舟の発着場跡というのがあります。船を使って物資を輸送していた名残だそうです。高瀬舟というのは、京都の高瀬舟と同じものだそうです。旭川の本流から水路が引かれていて、その横にプラットホームのようなものがあります。
ここから、町中に入っていきます。出雲街道の通っているあたりが、町並み保存地区です。古そうな建物はあるのですが、新しく建てられたものか、由緒のあるものかは見ただけではよく分かりません。車が時々通ります。ガイドマップには駐車場がこの通りの中に何カ所かあるように書かれています。
丘のお寺と桜の花です。花は見頃は過ぎているようです。お寺はたくさんあって、町並みに、趣を与えています。
軒先に置かれていた、回転砥石です。最近は合成研磨剤製のものがあるので使われなくなっているのでしょう。
街道から脇道に入り階段を上っていくことにします。上にあったのは文化往来館ひしおと安養寺です。ひしおは明治時代の醤油倉を改築して文化発信基地として使われています。名前から見ると地域の文化センターみたいで、よそ者にとって入りづらい場所でした。安養寺は、勝山藩主三浦家の墓所のある場所です。
ここの斜め前の道を進んでいくと、勝山で唯一残されている武家屋敷があります。家老格だった渡辺家の建物です。
中は有料ですが公開されています。中庭越しに見た、主屋と土蔵です。塀の外壁は白漆喰だったのですが。どちらの建物も、土色の壁になっています。
屋敷の前の道を進み、突き当たったところから右折すると下から見えていた、桜と明徳寺にでます。ここから石段を降りていくと、元の出雲街道に戻ります。街道に出る前に小さな用水路を渡ります。高田用水です。その横に、大事に使われているような井戸があります。桶がいくつかかかっていて、干支が書かれています。釣瓶にかかっているのは猿の絵が描かれたものです。
ここから、駐車場に戻る橋はすぐ近くです。橋の手前の文化センターや木材市場の前にあったしだれ桜は満開でした。木材市場の桜です。
車まで戻ってきました。次の所に行くことにします。
勝山から少し北上すると、日本の滝100選にも選ばれている神庭の滝があります。落差が100mを越える滝です。寄って見ることにします。
標識通り進んで滝の駐車場に到着します。ここから、滝までは徒歩になります。最初に道路右側に玉垂れの滝というのがあります。落差は2mほどなのですが、細い水の流れが無数に落ちています。滝上にある平らな岩の表面に生えたコケの中を水がしみるように流れてできているようです。
大阪大学のニホンザル研究所を過ぎるとゲートがあります。ここから先は有料になります。ゲートの先から山の斜面を登っていく道が分岐します。ここを進むと鬼の穴に行きます。10分ほどでつきました
鬼の穴は鍾乳洞です。その入口です。普通の横穴です。
中の壁はそれほど溶かされたというような模様も、鍾乳石が沈着したような所もありません。単に崩れ落ちた岩のようです。奥行きは、100mほどの区間は照明で照らされます。その先も続いているようですが、立ち入り禁止になっています。
ここで引き返すことになります。途中の壁に黒いものが見えたので何かとよく見たらコウモリが何匹か集まって休んでました。
滝道に戻って進んで行きます。すぐに滝に到着します。
滝の少し下流側は、広場になっています。木の上で鳥がきれいな声で鳴いていました。写真で確認したらキセキレイのようです。羽根の白い斑点が見えればすぐに分かったのですが、高いところに止まっていたのでこれ以上は無理でした。
ここから、滝に近づく道の途中にいろいろな花が咲いています。一番多かったのがミヤマカタバミです。写っている葉っぱは別の植物のものです。
このあたりは猿が集団で現れるところらしいのですが、1匹もいませんでした。数匹なら良いのですが、集団となるとちょっと怖い感じがします。
滝をじゅうぶん鑑賞したら駐車場に引き返します。滝の次は、醍醐桜を見に行く予定です。道は勝山まで戻り、国道181号を出雲の方に少し進んで、途中から姫新線沿いの道に入ります。あとは左側の山の中にあります。地図には詳しい道が書かれていませんが、標識があるようなのでそれに従っていくことにします。左折の道に注意しながら進んで行くといきなり岩井畝への標識がありました。岩井畝の大桜は、醍醐桜の先ですから来すぎたようです。引き返すのも面倒なので、このまま岩井畝の大桜を見に行くことにします。
岩井畝の大桜です。樹齢800年のアズマヒガンという品種だそうです。ちょうど満開のようです。
花のアップです。わずかに散り始めているようですが、花を見る限りではまだのようです。
横にあるヤブツバキもきれいに咲いていました。赤い点々状の模様ががきれいです。
そばの田んぼの縁にあった桜です。こちらも満開のようです。同じ品種でしょうか。
醍醐桜を見損ねたので見に行きたいのですが、そちらの方から来たという人に聞くとここから行く山道は一方通行の逆走になって行けないようです。元来た道を引き返すしかないようです。
醍醐桜へはこちらからでは、姫新線沿いの道から左折してから高架でまたいで行くようになっています。反対側に注意していたので見落としたようです。この道を進んでいきさらに右折して山の中に入っていったところにあります。
山の中に入るところにカタクリの咲いているところがあるので寄って見ました。ここのカタクリは、大地区のものより密集度が少ないようです。花も幾分か元気がないようです。時間帯のせいなのか、時期的な問題なのかはよく分かりません。日陰になっています。
周りにある細い葉っぱは、キツネのカミソリだそうです。これだけあると花の時期も見事と思われます。カタクリがまけるので、邪魔だと抜いてもらって良いといわれました。いっしょにカタクリも抜いてしまいそうです。
いっしょに咲いていた花です。名前は分かりません。
ニリンソウです。こちらの方が群生して咲いているところがありました。
アマナも咲いているというので教えてくれました。終わりかけで頭が下を向いていたのですが、起こしてくれたので写しました。
ここから山の中に入っていくと、醍醐桜があります。何台か続いた車の後ろの方になっています。桜の手前にある駐車場は満杯ですが、1台だけ出て行ったので先頭車だけが駐車できました。後続の車は、桜を過ぎてかなり上ったところの駐車場になります。何とか駐めることができましたが、シーズンでは入れない車もいるのではと思われます。
桜まで降りていく途中にもいろいろな花が咲いています。庭先で咲いていた木瓜の花です。
道ばたでは、シロバナタンポポが咲いています。このあたりではたくさん見かけます。
道沿いから見えた醍醐桜です。遠くから撮っています。大きな桜で、一本だけ丘の上にあります。樹齢千年のアズマヒガンだそうです。
横に、二代目というのが植えられていました。
二代目の花です。葉っぱもだいぶ大きくなってきています。
こちらが初代の花です。青空との対比がきれいなところです。
ここは人が多く、誰も写っていない所を撮るのは難しいようです。いろいろな角度から桜を見たら、ここは終わりにして、次に向かうことにします。
コースとしては、新見に抜ければ良いのですが、いったん醍醐桜の入口までもどり北房ICに抜けるか、真っ直ぐ進んで北房ダムに抜け高速道路沿いに進む、岩井畝を通って北房ダムからの道の合流する、岩井畝から姫新線沿いに進む4通りの方法があります。この時点で高速道路に入るという選択肢は省かれています。北房ダムからしばらくは道が狭そうなので除外すると、3番目のコースが一番近道のようです。この道をとります。
結局、途中は何もなく進んで行きます。新見の市街地を抜け、哲西町の鯉が窪という道の駅で休憩を取りました。近くに湿原があるようですが、よっている時間はないようです。それに何となく来たことがるような気がします。帰ってから調べてみたら7年前に来ていました。
ここから庄原に抜ける道は遠回りになる上、かなり遅い時間になっているので、高速道路を使わないといけないようです。ちょっと進むと広島県に入り、そこの東城ICから庄原ICまで高速道路を走りました。それでも途中で、宿に電話を入れなければいけない時刻になっています。庄原ICについてから電話をするとまだそこから50分かかると言われます。
宿への道を走っていきます。道路沿いの気温表示はだんだん下がっていき、まだ山中に入らないうちに一桁になっていました。山の上の気温はどれほどか気になります。
宿に着いた時には、薄暗くなり始めています。西の空はまだ明るいようです。すぐに食事を済ませ、宿の前で星の様子を見ます。宿の明かりのせいか、それほど星は見えません。駐車場に明かりがついていないので大丈夫かと思ったのですが、フロントで駐車場が暗くて怖かったと苦情を入れている客がありました。その後、駐車場の明かりがつけられました。これで、駐車場も使えなくなりました。
軽く体を洗ったあと、手元にあった服を着込みます。フロントに行き、星の見える場所を聞いてみます。道路から宿に入る分岐点にあった広場が良いそうです。そこに行ってみることにします。
直径が2−30m位の広場で明かりはないのですが、高い樹木に囲まれています。30度近くの高さまでは星は見えません。北極星もかろうじて木の上に見えます。何とか望遠鏡をセットして写真を撮り始めたのですが、極軸は合っていない、ピントはあまい、狙ったところの星が入らないはで散々です。極めつけは到着が遅れたのもあって、時間がほとんどなかったことです。何を撮ったのかよく分からない星の写真です。
宿は、吾妻山山頂近くの標高1000mの所にあります。裏側の窓からは、吾妻山が見えます。夜明け前の吾妻山です。
裏庭にあたる方角には、小さな池がいくつかあります。
宿の建物を出て、この池のある方向にでると、吾妻山に登っていく道に続いていきます。山に登ってみることにします。池のあるあたりから、しばらくは草も刈り込まれていて、空はよく見えます。宿の明かりはあるかも知れませんが、ここだとたくさんの星が見えたようです。所々にモグラ塚ができています。
ちょっと登ったところに大きめの池があります。原池といいます。
途中から、登山道みたいに坂がきつくなります。ホオジロがいて、歩いて行く先に逃げては枝に止まります。
ウグイスも良い声で鳴いています。飛んで行った先にある枝に止まったような気がしたので、カメラを向けてみたのですが、紛らわしい形の葉っぱがあります。そこよりわずかに右下の枝先でした。隅っこにかろうじて写っています。画像を確認している内に飛んで行ってしまいました。
稜線にでると、東の空が見えてきます。太陽は雲の中のようです。日の出は見えませんでした。
宿付近のようすもよく見えます。そこを中心に散策コースやキャンプ場などがあります。このなだらかな地形はどう見ても地滑りによってできたもののようです。
吾妻山の山頂です。向こうに移っているのは比婆山です。岩質は火山岩のようです。中国山地脊梁部で、もともと標高が高いところに、火山噴出物によってさらに高い山になったようです。
ここから宿に戻るには、このまま進んで南の原というとこに降りるコースと、来た道を引き返すコースがあります。このまま進むと時間が相当かかりそうなので、引き返すことにします。
ほとんど降りて、宿周辺の散策路あたりまでくると、いくつかの花が見られます、ふきのとうの花です。
裏庭の池の縁で咲いていたミズバショウです。
宿まで戻ったのですが、まだ食事まではしばらく時間があります。キャンプ場の方とかもみておくことにします。
キャンプ場へは、駐車場から道路に戻って分岐にある広場から入っていくことになります。駐車場に出たところで、鳥のさえずりが聞こえてます。木の先に止まっているのが見えます、ノビタキでしょうか。
キャンプ場に入ります。ここの駐車場も広く、周りの木もそれほど高くないので、昨晩星を見たところよりは、観測条件はよかったようです。見落としているかも知れませんが、街灯は見当たりません。
そのまま奥に進んでいくと水源地という場所に着きます。小さな小川が流れています。
林の中を進む道があったので、歩いていると、両脇に池が見えてきます。そのうちの右側に見えたひょうたん池です。
ここの池の縁にもミズバショウが咲いています。花が水面に映ってきれいです。
ここから、林の中を横切ると原池と宿の間の広場に出ました。食事の時間にはまだ少しありますから、朝風呂で汗を拭いてから行くことにします。早朝は、だれもいっていなかったせいなのか、湯につかるのには熱すぎました。
食事を済ませて、出発します。今日の予定です。調べてみた範囲内ではこれと言ったものは見つけられませんでした。麓の比和の町に博物館があって備北層群から出たくじらの化石などが展示されているみたいですが、パスします。奥出雲町にある鬼の舌震は前に来たことがあるので、これもパスするとすると興味が残るのは、たたら関係の施設ぐらいです。どこか他にもあるだろうということで、とりあえず北上して、高野の道の駅で情報を得ることにします。何もなければ、自動車道を北上して、出雲の方に行くことにします。
高野の道の駅です。かなり混んでいて、車を駐めるのに駐車場を1回回りました。今日は土曜日だからでしょうか。あまり資料はなかったのですが、ポスターに木次から三次に行く道の途中にさくらの名所が点在しているみたいなことが書かれていました、パンフはなかったのですが、この道を行くことにします。
自動車道は、木次三刀屋ICまでは新直轄道路ということで無料です。その分なのか、IC内には交差点があります。木次三刀屋ICでほとんどの車が降ります。高速料金は高いと思っている人が多いのですね。
道の駅で見た情報では、木次の斐伊川沿いの堤防の桜並木がきれいだとか書かれています。寄ってみます。斐伊川を渡る手前に駐車場の標識があったので入っていったのですが、車は駐まっていません。周りにも、入口以外はこれ言って桜の木は見当たりません。もっと別の所に駐車場があるだろうということで車を移動させます。もとの道路に戻って川を渡った右側に桜並木が見えます。こちらだったようです。並木沿いに車を走らせ駐車場を探しますが、行きすぎて、再び小さな川を渡ったところにありました。これでも、先ほどよりはだいぶ近くなりました。帰ってからパンフの地図を確認していると、八俣大蛇公園と書かれている場所のようです。
駐車場から斐伊川を渡る沈下橋があります。木の柵は流れを弱めるためのものでしょうか。
堤防の桜です。だいぶ花は散ってしまっています。
この小さな橋を渡って、桜並木に入ります。風が吹くと一斉に花びらが舞い降ります。
花びらが流れるように撮ってみました。コントラストがなくなってかえって何か分かりませんね。
落ちた花びらは、道の脇につもっています。
川に流されていくものもあります。
この一画だけ、咲いていた花です。何か分かりません。桜草でもないようです。
サクラの花が終わりかけていたのは残念です。次に行くことにします。
地図を見ていると、雲南市の外れに加茂岩倉遺跡と書かれている場所があります。どんなところか気になるのでいってみます。いったん国道に出て北上していけば西側にあります。違う遺跡の名前が出ていたので間違えて左折しましたが、元に戻り正しい所に着くことができました。
遺跡の駐車場や遊歩道の車止めは銅鐸の形をしています。何か関係があるのでしょうか。案内板には、ここから銅鐸が39個まとまって発見されたと書かれています。この近くには、荒神谷遺跡や西谷古墳群があって、順番に巡るコースになっているようです。今日はこの順番にまわることにします。
谷の間の遊歩道を進んで行きます。ここではシデコブシの花が見られました。
遺跡は、斜面を登ったところにあります。出土状態をレプリカで復元しています。彫り上げた土の中に見つかったものを、仮置き場として置いていた場所の状態です。
実際に発掘された場所の状態です。
銅鐸の中に別の銅鐸が入っているものが見えます。淡路島でも最近になってこのようなものが見つかったようです。
谷の奥、峠の所に橋のような形をした展示施設(ガイダンス)があります。そこからここまでは、木道が続いていて、車いすでも見学できるようになっています。
木道を歩いてガイダンスまで行きます。道沿いはトカゲの天国のようです。至る所で見かけます。カナヘビです。穴に入ろうとしています。
こちらは、ニホントカゲ。板のすき間に挟まっています。
斜面はいろいろな種類のスミレが咲いています。白い色をしたタチツボスミレです。
ガイダンスから見た、銅鐸発見場所です。見て思うのは、どうしてこんな山奥に埋めたのかが不思議です。
ガイダンスは、遺跡の解説や出土品のレプリカの展示があり、発見時のビデオも見られます。
ここで見つかった銅鐸には、いろいろなものがあります。これは出雲様式といわれるもので、この近辺しか見つかっていないようです。銅鐸の胴にある絵の間に書かれた帯の形に特徴があります。出雲で作られたのではないかといわれています。
銅鐸の釣り手の部分に×印が付けられているものです。不良品ではなく、魔除けだそうです。これから行く荒神谷遺跡で見つかった銅剣にも同じ印があるものが多数出土しているそうです。他にもウミガメとかトンボとかの書かれたものが展示されています。
使用されていた当時のさびの浮いていない複製もあります。色がきれいで、新たな発見でした。三角縁神獣鏡という鏡の出土した場所もこの近くにあります。ここに来る途中に間違えていこうとした場所です。そこも含めて、この付近の遺跡巡りとします。
遺跡巡りのコースは、加茂岩倉遺跡のガイダンスで確認済みです。いったん国道に戻り、北上して高速道路のICの手前にある広域農道を西に進んでいけば、右側にあります。
加茂岩倉遺跡の、駐車場に戻ったところで、岩倉の名前の元となった大岩を探します。ニワトリの鳴き声を聞いた者は宝を手にすることができるという金鶏伝説があるそうです。
荒神谷遺跡までは道が分かっている分スムーズにたどり着きました。付近は公園になっています。ここの駐車場の車止めも銅鐸ですが、表面の模様がはっきりつけられていません。
公園の入口に博物館があります。有料ですが、それほど高くないので入ろうとしましたが、料金は倍になっています。特別展をやっていたためです。興味のある内容ではありませんでした。展示は、発掘場所の復元、出土品のレプリカ、復元品の展示が主です。
博物館の建物です。公園内側から撮っています。
園路に咲いていた花です。梅なのか桃なのかよくわかりません。どちらでもないようです。
道ばたには、紫色の花が一面に咲いていました。スミレと思ったのですが、よく見るとカキドオシでした。
谷底の水田のような場所には、ハスが植えられています。遺跡から出土した種子から発芽したものだそうです。ハスの仲間には大賀ハスのように耐久性があるのでしょうか。2000年ハスといいます。
遺跡はこの奥、左側の森の中に入っていったところにあります。山の中に隠すようにある感じがします。
ここの遺跡も高いところにあります。発掘時のようすが復元されています。
左側の階段を上ったところにある、銅剣が400本近く埋まっていたようすです。整然と並べられています。
こちらは、その右側にある銅矛と銅鐸が埋められていた場所のようすです。コケが生え始めていて色が変わってきています。見学は、20mほど離れた反対側の斜面から行います。
山の中で咲いていたミツバツツジです。
青銅器が大量に埋められるようになったのは、古墳ができ始めたのと関係しているのではないかと考えられています。次に見に行くのは、その古墳のはしりのようなものがある場所です。
西谷古墳群に行くには、同じ公園内にある弥生の森博物館の標識を頼りに進んで行った方が良さそうです。広域農道を西に進んでいきます。途中で、右側へという標識が出ます。道路沿いと聞いていたので、もうついたのかと思ったのですが、その道は延々と続きます。今度は左折の標識がでます。そのまま進んで行くと元の農道に出てしまいました。遠回りしていたのでしょうか。途中道路沿いに滑走路を住宅地に変えているような感じの土地がありました。昔の飛行場かなと思ったのですが、調べてみると自衛隊の訓練場のあとだったようです。運転中だったので写真は撮れていません。
斐伊川を渡ったところで公園に到着しました。駐車場から丘を上がったところに古墳群があるようです。登り道は昔からの里道で観音坂と呼ばれていたそうです。坂を登り切って最初に見えるのが4号墓です。方墳のように見えますが、四隅が張り出しているのが特徴です。手前側に伸びてきています。四隅突出型墳丘墓(よすみ)というのだそうです。弥生時代のものだからか、古墳と呼んでいないのにあとで気が付きました。古墳時代のものは、17号墳というように古墳扱いです。
すぐ北側に、3号墓が見えます。こちらのよすみは石で囲ってあるので形がよく分かります。分かるように置いたのではなく、輪郭部だけ復元したようです。
上に上ることができますので、上がります。周りの景色がよく見えます。さらに北側の2号墓です。こちらはできた当時のままに石で覆っています。1号墓はその向こうの林の中にあります。
反対側の、4号墓・5号墓です。こちらは形が分かるように木が伐採されています。
3号墓の上には埋葬状態が分かるように、出土品の並びが書かれています。赤いところが、木簡が埋められていたところです。古墳と違って石室のようなものはありません。
2号墓のよすみです。墳丘墓に上がる道として使われていたという説があるようです。上がれるようになっている隅から上がっていきます。
2号墓の上です。四角いようすがわかります。長方形になっています。向こうに見えるのは3号墓です。
2号墓を東側丘の中段より見上げたところです。見える斜面には、墓穴がたくさん見つかったそうです。横穴墓群というそうです。ここよりは、もう少し右側のようです。2号墓にある、入口のようなものは中が展示施設になっていてそこへの出入りのためのものです。復元時のようすが解説されています。
墳墓群は、このほかにも駐車場から見えるものとして、横穴墓群第3支群があります。白く見えているところが穴を掘ったあとだそうです。古墳時代のものなので、玄室が作られているそうです。
さらに左側、道路の先には、第9号墓があります。林の向こう、頂上が平らな丘がそれです。
四隅突出型墳丘墓は弥生時代の終わり頃に現れた墓で、加茂岩倉遺跡や荒神谷遺跡よりわずかにあとの時代のものだそうです。似ているので古墳と勘違いしていました。埋葬のしかたが全く違います。これらのものが作られたあと、国内ではすぐに、前方後円墳が作られるようになったようです。
西谷墳墓群のあるところは史跡公園になっていて、出雲弥生の森博物館が併設されています。墳墓のあるところから谷の向こうに見えます。
博物館に降りていく途中にある芝生広場のさくらがきれいに咲いていました。
弥生の森博物館は、西谷から出土した品の展示の他、墳墓での葬祭のようすが模型で作られています。小さな人形で、人の動きが再現されています。この博物館は、西谷だけではなく出雲付近の遺跡の出土品も保管されていて見ることができるようになっています。
弥生の森史跡公園は以上にします。この近くの出雲市内にも遺跡や古墳はたくさんあるようですが、先のことを考えて戻ることにします。このまま、斐伊川に沿って遡っていくのが予定している帰り道になります。途中にある神原神社古墳というのが気になります。加茂岩倉遺跡のあった加茂へ向かう支流沿いにあります。加茂に抜ければ、国道沿いに走れば、再び斐伊川に戻ることができます。
途中から支流側に分岐し、遡っていくと橋を渡って500mで神原神社古墳という標識にであいます。そのまま橋をわたって真っ直ぐ進んで行っても、それらしいものは見当たりません。橋まで戻って上流側に100mほどいったところに、遺跡がありました。
遺跡は、道路となっている堤防にかかってしまったために、発掘時のようすを復元して見られるようにしています。そのままでは風雨にあたるので屋根が作られています。
この下にある、復元された石室です。解説の写真がかかっていますが、だいぶ色あせています。右から二つ目にかかっているのが、ここで発掘された三角縁神獣鏡です。魏志倭人伝で、卑弥呼に贈られたと書かれている、鏡の内の一つとされています。
こちらが、神原神社の本殿と拝殿です。本殿は、古墳の上に立てられ、土台の一部が石室にかかっていたそうです。このすぐ後ろが堤防になります。
神原神社には、その大きさの割に立派な随神門があります。奥に見える拝殿とともに。大きなしめ縄が飾られているのは、出雲地方の神社の様式なのでしょうか。
このあたりには人気がないので、次に向かうことにします。支流を遡り国道に出ますが、その前に近くに安いガソリンスタンドがあったので給油していきます。
国道を北上し、木次に出たら支流の三刀屋川の沿って進みます。進んできた国道を真っ直ぐ進むことになります。三刀屋の町中でも川の堤防に沿って桜がたくさん咲いていました。このあたりにもさくらの名所の印がありましたが、斐伊川堤防と同じでだいぶ散っているのではとパスしました。調べてみると、御意黄という種類の桜があったようです。黄緑色の花が咲きます。ソメイヨシノよりは遅めなのでまだ咲いていたかも知れません。
国道を走っていきます。すぐに、滝への分岐と道の駅の案内がほとんど同時にでます。道の駅で、情報を入手してからと思いそのまま走らせ続けますが、なかなか道の駅に着きません。そのうち分かったのは、10km以上先だったということです。再び同じような感じで標識がでますが、今度は滝の方を優先することにします。10分ほど走らせて駐車場に到着です。ここからは歩きになります。
駐車場前の川は、庭園風に飾られています。
日は陰り始めています。山桜の花が際立って見えています。
ニリンソウです。暗くなってきたせいか、花は閉じています。
ムラサキケマンの花です。今回始めてみました。
ここから道を進んでいった先にあるのは龍頭が滝で、滝百選にも選ばれているそうです。
竜頭の滝は、雄滝と雌滝の2つがあります。下流側にあるのが雌滝で、そこから雄滝まで真っ直ぐ登っていくことができないので、2つの滝に行く道が分かれます。分岐点付近には、大きな杉の木の林があります。
まずは、雌滝に行きます。滝の下と思われる場所で道が行き止まりになるのですが、川の水が傾斜のきついところを流れているのが見えるだけです。どう見ても落差が30mもあるようには見えません。左上の滝は本流の流れに比べて細すぎます。上の方で時々しぶきのようなものが見えます。さらにこの上の岩向こうに雌滝があるようです。付近を探してみたのですが、この先に滝に近づく道はありません。あきらめて引き返すことにします。
分岐点まで戻り、雄滝に行く道に入ります。途中の林のすき間から雌滝らしきものが見えました。
雌滝の上にまわったところで、雄滝が見えてきました。
滝に近づくことができます。滝の下半分の向こう側は洞窟になっています。
左側の斜面から、洞窟に入ることができます。かがまないと進めないところもありますが、滝の裏側に回ることができます。これ以上近づくと、滝のしぶきがかかってびしょ濡れになります。
洞窟の左上側に滝観音が祀られています。
反対の右側からも入ってみました。こちら側は天井からの水のしたたりが多いようです。
引き返す途中、道沿いに紫色の花の群落がありました。こちらのものはカキドオシではなく、スミレでした。
アセビの花も咲いていました。
滝から元の国道に戻り、しばらく走ると道の駅に着きました。閉店時刻を過ぎていました。建物の裏の公園につながる道沿いのソメイヨシノはすっかり散ってしまっています。路面は桜の花びらの絨毯になっています。
もう遅くなっています。このまま高速道路で帰っても、中国道宝塚トンネルの渋滞は解消しているでしょう。
近くの吉田掛合ICから自動車道に入ります。道路は、対面通行で所々で追い越し可能区間があります。何台かの車に追いつかれたのですが、みんな追い越していかずに後ろについてきます。そのまま三次東JCTについてしまいました。町のスーパーで軽く食べるものを買いたかったので、いったん自動車道を降ります。三次の方に行くつもりだったのですが、庄原も10kmちょっとの距離だったので行き先を庄原に変更します。庄原についてそれらしい建物を探しました。国道沿いの目立つ建物はホームセンターとかでスーパーはありません。町中の方に行ってみたのですが、ここでもそれらしいものは見かけません。駅前にでてしまったので、駅の地図で確認してスーパーにたどり着くことができました。
庄原ICから高速道路に入り、大阪に向けて走ります。三田から宝塚にかけての渋滞区間での、渋滞の案内はありません。順調に走り事ができました。宝塚も渋滞もなくスムーズの通りに抜けます。となると、どの車も車間を詰めて高速で飛ばしてきますので、今度は怖くなってきます。もたもた走るわけにはいかないので必死でハンドルにしがみついています。これだけは何とかならないものでしょうか。
<観光場所>
今回の旅行の行き先のメインは花と滝と遺跡になりました。まわる場所にしても、パンフをよく読めば、もう少し巡ってみたい場所があったようです。真庭にしても、パンフに書かれているのが、土産物屋と食べ物屋ばかりだ(と思った)のがよくなかったようです。パンフの置いてある場所で立ち読みではなく、座って広げられるところでじっくり見た方がよかったようです。
あらかじめ調べておくという方法もありますが、行った先で他の資料に埋もれて、戻ってから、こんな資料があったのだと再発見することもありました。どちらが良いのでしょうか。
宿の到着が遅くなってしまいました。無計画なのがよくないのでしょか。一応この時間までには、ここを通過するというのは決めていましたが、寄り道のしすぎで遅れがちになっていました。でも、何もないところは本当にないので、早く着きすぎてしまうこともあります。このあたりの調節はどうすれば良いのでしょうか。時間の計算も間違っていた事も遅れた原因の一つです。
旅行会社のツアーでは時間が決められています。ここまで設定するには、それなりに調べておくことがたくさんあるでしょう。それでも時間が足りなかったり、すぐに終わってしまったりすることがあります。おもしろそうな所が見当たるとそこにも行って見たくなります。どちらかというと、臨機応変にやりたいので、今のやり方の方がいいでしょう。
<星の写真>
地方に出かける目的の1つに、星の写真を撮ることがあげられます。今回は、完全に失敗でした。到着が遅れて観測場所の下見ができなかったことのほかにも、機材が使いこなせなかったのも原因しています。ふだんは、視野の中に狙った星を簡単に入れられるのですが、今回は狙い通りにはいきませんでした。何が原因だったのでしょう。
ファインダーがずれていたのも、それが原因しているようにみえます。締め付けが甘く、まだちょっとぐらついているところもあります。取り付け台に無理に差し込んでいたので、留め金が曲がっていたのもあります。このあたりの修正方法は、検討の余地があります。それでも、最初に目的の星がファインダーの視野の中に入っているかも確認できませんでした。最初にファインダーの向きを調節したときに、違う星を視野の中心に入れていたのかも知れません。何か変だとは思っていたのですが、そうならそこできちんとしておくべきでした。
前回が初めてにしてはスムーズにいったので、今回は気が緩んでいたのでしょう。次回は慎重に行きたいものです。
<遺跡>
2日目は、遺跡巡りになってしまいました。まわっていて分かったことなどを整理しておきます。古い順に書いていきます。
時代的には弥生時代で、2000年ほど前のことになります。それまでは、青銅器が使われていました。銅剣や銅矛・銅鐸です。畿内から持ち込まれたものもありますが、出雲地方で独自に作られたものもあります。初期のものは、銅剣のように実際に使われていたのですが、次第に祭祀の用具へと使われ方が変わってきたようです。それが、何らかの理由で、まとめて埋めないといけない事態になります。これは憶測になりますが、鉄器のような新しい道具とともに、信仰も導入されるようになったのでしょう。そのため、いらなくなった祭祀の用具は破棄されますが、古い信仰を捨てきれない人たちがこっそり山奥にまとめて埋めたのではないでしょうか。このようにしてできたのが、加茂岩倉遺跡や荒神谷遺跡です。最近淡路島で発見された大量の銅鐸も同じようにして埋められたものでしょう。
同時に、国家の態勢も変わったようです。今までより広い範囲を、より大きな権力を持つものが支配するようになります。その権力によって、墓も大きくなり大きな塚が作られます。このようにして作られたのが四隅突出型墳丘墓です。これは出雲地方独特のもので出現時期は青銅器が大量に埋納された時期と重なります。墳丘墓からは、鉄剣も埋葬品として発掘されています。
出雲に巨大な墳丘墓が作られるようになったころ、卑弥呼が魏に使者を送ります。アクセサリーをたくさん埋葬した女王と、鉄剣をいっしょに埋葬した男王の墓が同じ墳丘墓にあることからみて、出雲は女王が支配した邪馬台国ではなく小国の一つようです。
その後、大和朝廷なのか邪馬台国の影響なのか、墓の形は墳丘墓から古墳に形が変わっていきます。三角縁神獣鏡は、そこに書かれている年号から、魏から卑弥呼に贈られたものと考えられていて、その一つが出雲に持ってこられ、最終的に神原神社古墳の埋葬品になったようです。
<経費>
今回の旅行で使った費用です。
交通費 18000 高速道路・ガソリン・駐車料
宿泊費 9000
その他 4500 入場料・食事・土産
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
合 計 31500